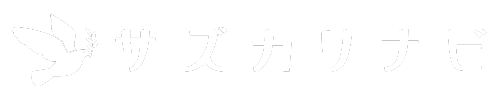「なかなか子宝に恵まれないのはなぜだろう」「自分たちに何か原因があるのでは?」と悩んでいませんか。不妊や妊娠のしづらさに直面したとき、年齢や生活習慣、体の状態など、どこを見直せばよいのか分からず不安になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、子宝に恵まれない人の特徴を医学的・生活習慣の両面から徹底解説し、妊娠しやすい体づくりのために今日からできる具体的なアクションを8つ紹介します。不妊の定義や現状、よくある質問も紹介しているので、夫婦で前向きに妊活へ取り組むための参考にしてみてください。
子宝に恵まれない人の主な特徴【医学的要素編】

厚生労働省の「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」によると、妊娠を望む夫婦の約4.4組に1組が不妊の検査や治療を受けているといわれています。ここでは、子宝に恵まれない人の主な特徴を医学的な観点から詳しく解説します。
- 年齢
- 不妊に関する検査や治療が不十分
- ホルモンバランスの乱れ
- 持病や婦人科系疾患
- 男性側の精子の質や量の問題
参考:厚生労働省「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」
年齢
年齢は、不妊に影響を与える最も大きな要因です。女性の場合、卵巣に含まれる卵子の数は加齢とともに減少し、卵子の質も低下していくため注意が必要です。
| 年代 | 1回で妊娠する確率 |
|---|---|
| 20代 | 約25〜30% |
| 30代前半 | 約25〜30% |
| 30代後半 | 約18% |
| 40代 | 約1% |
厚生労働省によると、20代の妊娠する確率は約25〜30%ですが、それ以降は徐々に低下し、40代になると約1%まで低下する可能性が指摘されています。
また、体外受精の成功率も年齢とともに低下し、20代では約40%以上なのに対し、30代前半では約35%、30代後半で約25%、40代では約10%となり、45歳以上では5%未満となっているため参考にしてみてください。
男性も同様に、加齢に伴い精子の量や運動率が徐々に低下し、受精率が低下することが知られています。
参考:日本生殖医学会Q24.加齢に伴う卵子の質の低下はどのような影響があるのですか?、日本生殖医学会Q25.男性の加齢は不妊症・流産にどんな影響を与えるのですか?、厚生労働省 不妊治療の実態に関する調査研究 最終報告書、2022年体外受精・胚移植等の臨床実施成績
不妊に関する検査や治療が不十分
不妊の原因を正確に把握するためには、夫婦両方が適切な検査を受けることが重要です。一方で、検査や治療を受けるタイミングが遅れたり、検査が不十分だったりすると、妊娠の機会を逃してしまうことがあります。
一般的には、妊娠を望む健康な男女が避妊をせず性交渉を行っても1年間妊娠しない場合は不妊とされ、医療機関の受診や治療が推奨されています。一方で、年齢が35歳以上の場合は早期の受診がおすすめとなっており、期間に縛られることなく早めに専門医に相談することが重要です。
不妊治療の成功率は年齢が若いほど高くなるため、早期発見・早期治療が妊娠の可能性を高めてくれるでしょう。
参考:厚生労働省 不妊治療の実態に関する調査研究 最終報告書
ホルモンバランスの乱れ
女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンは、月経周期や妊娠の維持に重要な役割を果たすホルモンです。これらのホルモンは20代から30代前半にピークを迎え、その後徐々に減少していくことが知られています。ホルモンバランスが乱れると、排卵障害や月経不順、着床不全などが起こり、妊娠しにくい状態になります。
ホルモンバランスの乱れは、ストレスや睡眠不足、過度なダイエット、運動不足などの生活習慣の乱れによって引き起こされることが多いため、生活習慣を見直すことが大切です。
持病や婦人科系疾患
子宮内膜症、子宮筋腫、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)、卵管閉塞などの婦人科系疾患は、不妊の原因となることがあります。子宮内膜症は妊娠を希望する患者の30〜50%が不妊症を合併しており、卵巣や卵管周囲の癒着により卵子の取り込みが困難になったり、卵巣機能の低下により卵子の質が悪化したりします。
婦人科系疾患では自覚症状がない場合もあるため、定期的に健診を受診し、専門医に相談するのがおすすめです。
また、糖尿病や甲状腺疾患などの内分泌疾患も不妊に影響を与えることがあります。例えば、甲状腺機能低下症では月経異常や性欲低下が生じ、甲状腺機能亢進症では流産のリスクが上昇することが知られているため、注意が必要です。
これらの疾患は適切な治療により改善が期待できるため、早期発見・早期治療が重要です。
男性側の精子の質や量の問題
不妊の原因の約半数は、男性側にあることが知られています。男性不妊の原因の約80%は精子の量や質に問題があるケースとなっており、その中でも、精索静脈瘤は男性不妊の代表的な原因とされています。精索静脈瘤は、精子の状態に問題がある方の約4割に見つかることが多く、注意が必要な疾患です。
また、精子の質は、老化や加齢によるストレス、喫煙、睡眠不足、運動不足、肥満、不適切な食生活などによって悪化することが分かっています。基本的な生活習慣を見直すことで改善される可能性もあるため、自分にできることから積極的に改善していきましょう。
性機能障害による射精困難、精路通過障害による精液中の精子不足なども男性不妊の原因となります。気になる症状がある場合には、早めに専門医を受診するのがおすすめです。
参考:日本生殖医学会Q25.男性の加齢は不妊症・流産にどんな影響を与えるのですか?、Tanaka T, Kobori Y, et al. Seminal oxidation-reduction potential and sperm DNA fragmentation index increase among infertile men with varicocele. Hum Fertil (Camb). 2020 Jan 20:1-5.、Varicocele and semen quality: a retrospective case-control study of 4230 patients from a single centre
子宝に恵まれない人の主な特徴【生活習慣編】

生活習慣は妊娠に大きな影響を与える重要な要素です。日々の食事や運動、睡眠などの生活習慣が、ホルモンバランスや身体の機能に直接関わっている場合も多くなっているため、注意が必要です。
ここでは、子宝に恵まれない人に多く見られる生活習慣の特徴について、詳しく解説します。
- 喫煙や過度な飲酒の習慣
- 太りすぎ・痩せすぎなど体重の極端な変動
- 運動不足や血行不良
- 必要な栄養素の不足
- 睡眠不足や不規則な生活リズム
- 夫婦で妊活に温度差がある
喫煙や過度な飲酒の習慣
タバコに含まれる有害物質は卵巣や卵子の質を低下させ、女性の妊娠率を著しく下げてしまいます。さらに、喫煙は血管を収縮させるため子宮や卵巣への血流も悪化させ、着床環境を損なう原因となるため注意が必要です。
男性も同様に、喫煙によって精子の濃度や運動率が低下しやすく、DNA損傷のリスクが増加します。副流煙ですら受精障害や流産リスクの上昇に関係するといわれているので、カップルで揃って禁煙に取り組むことが大切です。
また、週に7杯以上のアルコール摂取は女性における不妊リスクを約2倍に引き上げ、男性ホルモンの低下や精子の質悪化を招く可能性があります。過度な飲酒習慣はホルモンバランスを乱し、肝機能に負担をかけることから、節度ある飲酒量にとどめるよう心がけましょう。
太りすぎ・痩せすぎなど体重の極端な変動
BMIが適正範囲から外れると、妊娠率に影響することが分かっているため注意が必要です。
BMI18.5未満の痩せすぎの場合、女性ホルモンの分泌が低下し、無月経や排卵障害を引き起こしやすくなる可能性が高くなってしまいます。一方、BMI25以上の肥満では、ホルモンバランスが乱れ、排卵障害や生理不順のリスクが高くなるとされています。
また、無理なダイエットや偏った食生活は、ホルモンバランスを崩し、排卵周期を不規則にするため特に注意が必要です。
BMIが高いからといって無理なダイエットをしてしまうと、急激な体重減少により体重減少性無月経を引き起こし、排卵が完全に止まってしまう場合もあります。妊活中は特に、極端な体重変動は避け、健康的な体重管理を心がけることが大切です。
運動不足や血行不良
適度な運動は血行を促進し、生殖器官への酸素や栄養素の供給を改善する効果が期待できます。運動不足が続くと全身の血流が悪化し、子宮や卵巣の機能低下につながる恐れがあり、注意が必要です。特に、現代人に多いデスクワークによる長時間の座位は、骨盤内の血流を滞らせる原因となっています。
また、血行不良は冷え性の原因にもなり、子宮内膜の厚みや質に悪影響を与える可能性があります。男性においても、精巣周辺の血流が悪化すると精子の生成に支障をきたすことがあるため、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を日常的に取り入れ、血行改善を心がけることが大切です。
ただし、過度な運動は逆効果となるため、適度な運動を続けていくのがおすすめです。
必要な栄養素の不足
妊娠しやすい体をつくるためには、バランスの取れた食事が重要です。鉄分や葉酸、ビタミンD、亜鉛などの栄養素は、卵子や精子の質を高め、着床や妊娠の維持に重要な役割を果たしているため、積極的に摂取したい栄養素です。
例えば、鉄分が不足すると貧血になり、全身の酸素供給が低下するため生殖機能も低下しやすくなります。また、葉酸は細胞分裂や胎児の発育に欠かせない栄養素のため、妊活中から必要量を摂取できるよう、食生活を見直していきましょう。
睡眠不足や不規則な生活リズム
睡眠は、ホルモンバランスや自律神経の安定に直結しています。睡眠時間が短い、または夜更かしが続くと、ホルモンバランスが崩れ、排卵や月経周期が乱れやすくなり、妊娠のチャンスが減ってしまいます。
特に、22時~2時の間は成長ホルモンの分泌が活発になるため、この時間帯にしっかり眠ることが重要です。規則正しい生活リズムを心がけることで、体内時計が整い、妊娠しやすい環境を作りやすくなるでしょう。
夫婦で妊活に温度差がある
妊活に対する考え方や取り組み方に夫婦で差があると、ストレスや孤独を感じやすくなります。
女性は月経ごとに妊娠できなかったことを実感しやすいのに対し、男性は身体的変化がないため実感がなく、楽観的になることも多いでしょう。この温度差がコミュニケーション不足や妊活の停滞につながることがあるのです。
この温度差を埋めるためにも、お互いの気持ちや不安を率直に話し合い、協力しながら妊活を進めることが大切です。夫婦で支え合い、前向きに妊活に取り組んでいきましょう。
子宝に恵まれるためにできること8選

妊娠しやすい体づくりや妊活の成功には、日々の生活習慣や心身のケアなどが非常に重要です。ここでは、子宝に恵まれるために意識したい具体的なアクションを8つ紹介します。
- 基礎体温などのセルフチェックを行う
- 食生活を見直す
- 禁煙・禁酒をする
- 生活リズムを整え、十分な睡眠をとる
- 適度な運動やストレッチの習慣化
- 自分に合ったストレス発散法を見つける
- 夫婦で妊活について話し合う
- 専門医に相談する
1.基礎体温などのセルフチェックを行う
基礎体温とは、朝目覚めてすぐ安静にした状態で測る体温のことです。基礎体温を毎日記録することで排卵日や体調の変化を把握でき、妊娠しやすいタイミングを見極めやすくなります。
また、基礎体温表を活用することで、ホルモンバランスの乱れや無排卵のサインも早期に気づける可能性が高まるため、妊活の第一歩としておすすめです。
また、卵巣年齢チェックや精子の運動量チェックなど、自宅で気軽にセルフチェックができる商品も増えています。自分の体のリズムを知ることで、計画的な妊活が可能になるだけでなく、専門医へ相談する目安にもなるため、気になる方はぜひチェックしてみてください。
2.食生活を見直す
バランスの良い食事は、妊娠しやすい体づくりの基本とも言えます。特に鉄分や葉酸、ビタミンD、亜鉛、タンパク質などは卵子や精子の質向上に欠かせない栄養素です。
野菜や果物、魚、肉、乳製品をバランスよく取り入れることが大切で、加工食品や糖質の摂りすぎは控え、栄養バランスを意識した食生活を心がけましょう。
食事の時間が不規則だったり、外食が多くなってしまったりする場合には、サプリメントを取り入れるのもおすすめです。
3.禁煙・禁酒をする
喫煙は卵巣機能や卵子の質を低下させるだけでなく、精子の数や運動率も悪化させます。同じように過度なアルコール摂取もホルモンバランスを乱し、女性では排卵障害、男性では精子の質の低下を招くことが知られています。
妊娠を望む場合は、夫婦そろって禁煙・禁酒に取り組むようにしてみてください。
4.生活リズムを整え、十分な睡眠をとる
規則正しい生活リズムと十分な睡眠は、ホルモンバランスの安定や体調管理に直結します。睡眠不足や夜更かしが続くと、排卵や月経周期が乱れやすくなり、妊娠のチャンスを逃しやすくなるため注意が必要です。
可能な限り同じ時間に寝起きし、7~8時間の質の良い睡眠を確保できるよう心がけていきましょう。生活リズムを整えるためにも、寝る前のスマホやパソコンの使用を控え、リラックスした状態で就寝する習慣をつけていくのがおすすめです。
5.適度な運動やストレッチの習慣化
ウォーキングやヨガ、ストレッチなどの適度な運動は、血流を促進し、子宮や卵巣への栄養供給をサポートしてくれます。筋肉量が増えることで基礎代謝も上がり、冷え性やホルモンバランスの乱れを予防しやすくなるためおすすめです。
適度な運動は身体に良い影響を与えますが、激しすぎる運動は体を痛めたり、ケガにつながったりと、逆効果となる場合もあるため、無理のない範囲で継続することが大切です。
6.自分に合ったストレス発散法を見つける
ストレスはホルモンバランスを乱しやすく、妊娠の妨げとなることがあります。趣味やリラクゼーション、友人との会話、軽い運動など、自分に合った方法でこまめにストレスを発散しましょう。
深呼吸や瞑想も、心身のリラックスに効果的です。道具を使わなくても手軽に取り入れられるため、ストレスを感じている場合には試してみるのもおすすめです。
ストレスをため込まず、前向きな気持ちで妊活に取り組んでいきましょう。
7.夫婦で妊活について話し合う
妊活は、夫婦で協力して進めることが大切です。お互いの気持ちや不安、希望を率直に話し合うことで、心の負担が軽減されるでしょう。妊活の目標やスケジュール、役割分担についても共有し、二人三脚で取り組むことが大切です。
なかなか話し合うタイミングがない場合には、LINEなどのコミュニケーションツールを利用するのもおすすめです。コミュニケーションを密にすることで、妊活のモチベーションも維持しやすくなります。
8.専門医に相談する
妊活を始めてから1年以上妊娠しない場合や、女性の年齢が35歳以上の場合は、早めに専門医に相談することをおすすめします。不妊の原因は女性側、男性側共に多岐にわたるため、適切な検査や治療を受けることが大切です。
また、妊活中は不安や疑問点が多く出てくるものです。専門家のサポートを受けることで、これらの悩みも解消しやすくなるでしょう。
もしかして不妊症?不妊の定義と現状

妊活を始めているのになかなか子宝に恵まれないと、「もしかして不妊症かもしれない」と不安になる方も多いのではないでしょうか。不妊症は決して珍しいことではなく、適切な知識を持つことで早めの対策や相談が可能になります。
ここでは、不妊の定義と日本における現状についてわかりやすく解説します。
- 不妊の定義とは
- 不妊の現状と割合
不妊の定義とは
不妊症とは、妊娠を希望する健康な男女が、避妊をせずに一定期間(一般的には1年間)性交渉を続けても妊娠に至らない状態を指します。この「1年間」という期間は、日本産科婦人科学会や世界保健機関(WHO)でも基準とされており、年齢や健康状態によっては半年程度で医療機関への相談が推奨される場合もあります。
不妊の原因は女性側だけでなく、男性側にもあることが多いため、夫婦で一緒に検査や相談を受けることが大切です。
不妊の現状と割合
日本では晩婚化やライフスタイルの変化などにより、不妊に悩むカップルが増えています。厚生労働省の調査によると、夫婦の約5~6組に1組が不妊の検査や治療を経験しているとされています。不妊治療を受ける方も年々増加傾向にあり、特に30代後半から40代で治療を始めるケースが多いようです。
こうした現状を踏まえ、早めの相談や正しい知識を習得することが大切です。
不妊症は誰にでも起こりうる身近な問題でもあるため、夫婦で協力しながら取り組んでいきましょう。
子宝に恵まれない人の特徴についてよくある質問

妊活中は、子宝に恵まれない原因や対策についてさまざまな疑問を持つことがあります。ここでは、特に多い質問とその回答を分かりやすくまとめました。
妊娠しやすい体づくりや不妊対策を考える際の参考にしてみてください。
- どのくらい妊娠しないと検査や治療を受けるべき?
- 仕事や日常生活で気をつけるべきことはある?
1.どのくらい妊娠しないと検査や治療を受けるべき?
基本的には、妊活開始後1年間妊娠しなかった場合の受診が推奨されています。
| 初めて医療機関を受診した年齢 | 人数(全体合計:1,636人) |
|---|---|
| 25歳以下 | 170人 |
| 26~30歳 | 467人 |
| 31~35歳 | 544人 |
| 36~40歳 | 355人 |
| 41~45歳 | 80人 |
| 46歳以上 | 20人 |
令和2年度に発表した厚生労働省の調査では、妊活のために医療機関を初めて受診した年齢で1番多いのは30歳の10.2%で、35歳の8.3%、33歳の7.9%と続きます。なお、平均値は32.45歳です。
| 妊活開始後の医療機関の受診タイミング | 人数(%) |
|---|---|
| 妊活を開始すると同時 | 540人(33.0%) |
| 妊活を開始後3か月程度 | 297人(18.2%) |
| 妊活を開始後6か月程度 | 281人(17.24%) |
| 妊活を開始後9か月程度 | 72人(4.4%) |
| 妊活を開始後12か月程度 | 149人(9.1%) |
| 妊活を開始後1年~2年程度 | 155人(9.5%) |
| 妊活を開始後2年~3年程度 | 86人(5.3%) |
| それ以上 | 56人(3.4%) |
また、医療機関を受診するタイミングについては、「妊活を開始すると同時に医療機関を受診した」とする回答が全体の33.0%となっていました。妊活開始後3か月程度で受診した方が 18.2%、妊活を開始してから6か月程度で受診した方が 17.2%と続き、全体の68.4%が妊活を開始してから半年以内に医療機関を受診しています。
医療機関を受診するのに、早すぎるということはありません。適切な検査や助言を受けることで、妊活中の不安を和らげたり、ストレスを軽減できたりする可能性もあるので、夫婦間で受診のタイミングについて相談してみるのがおすすめです。
参考:厚生労働省 不妊治療の実態に関する調査研究 最終報告書
不妊治療は早く始めるほど選択肢が広がるため、不安を感じた時点で積極的に専門家へ相談しましょう。
2.仕事や日常生活で気をつけるべきことはある?
妊活中は仕事や日常生活の過ごし方にも注意を払うことが大切です。長時間同じ姿勢を取る場合は、1時間ごとに軽いストレッチや歩行を取り入れ、体を動かす時間を意識してつくりましょう。
特に座りっぱなしが続くと骨盤の血流が悪化しやすいので、適度に姿勢を変えるのも効果的です。出勤や帰宅の移動時間に階段を使う、歩く距離を少し増やすなど、日常の中でできる運動量の確保も心がけていきましょう。
また、過度な残業や仕事のプレッシャーを抱え込み過ぎないことも重要です。ストレスが蓄積されると不妊のリスクを高めることが分かっているため、できるだけオンオフの切り替えを意識し、休憩やリラックスタイムをしっかり確保しましょう。
また、夜勤や不規則なシフトが続く方は、仮眠も取り入れながら体調管理を意識しましょう。会社や職場の理解が得られる場合は、必要に応じて勤務時間調整や休暇を利用し、心身の安定を優先してください。
まとめ:子宝に恵まれない人の特徴は様々、夫婦で協力して生活習慣を見直してみよう!

子宝に恵まれない原因は、年齢やホルモンバランス、持病や婦人科系疾患、生活習慣の乱れなど多岐にわたります。また、喫煙や過度な飲酒、運動不足や栄養不足も妊娠しづらさに影響します。さらに、夫婦間のコミュニケーションや妊活への温度差もストレスの要因となることがあるため注意が必要です。
妊娠しやすい体づくりのためには、基礎体温のセルフチェックやバランスの良い食生活、禁煙・禁酒、十分な睡眠、適度な運動、ストレスケアが大切です。夫婦で協力しながら妊活に取り組み、必要に応じて専門医へ早めに相談することも検討してみてください。
一人で悩まず、二人で支え合いながら生活習慣を見直すことが、子宝を授かることにつながります。
妊活を進める中で「産み分け」に関心を持つ方もいらっしゃいます。産み分けの方法としては、性交のタイミングで調整するなどがあります。
最近では、産み分けに関心のある方の間で潤滑ゼリー(一般的に「産み分けゼリー」と呼ばれることもある)が話題になっているようです。
産み分けに関する詳しい情報や、こうした潤滑ゼリーなどについて気になる方は、こちらの記事もご参考ください。