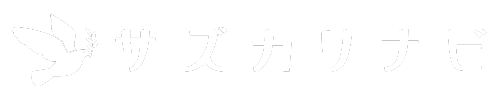妊活を始めると、「妊活中に納豆はダメって聞いたことがあるけど本当?」「納豆をたくさん食べるのは危険?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
納豆は、日本の伝統的な発酵食品で、栄養価も高いことで知られていますが、インターネット上には「妊活中は避けたほうがいい」という情報も見かけることがあります。
本記事では、妊活中の納豆摂取について、科学的根拠をもとに詳しく解説していきます。
ダメと言われる理由や妊活中におすすめの食べ方のポイント、納豆以外に注意が必要な食品についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
妊活中に納豆はダメ?NGと言われる理由とは

妊活中に「納豆はダメ」と言われることがありますが、実際は適量であれば摂取しても問題ありません。
ここでは、なぜ「納豆はダメ」と言われているのか、その原因について解説します。
- 大豆イソフラボンはエストロゲンと似た働きをする
- 過剰摂取はホルモンバランスを乱す可能性がある
大豆イソフラボンはエストロゲンと似た働きをする
納豆に含まれる「大豆イソフラボン」は、女性ホルモンの「エストロゲン」と似た構造を持つ植物性化合物で、過剰摂取するとホルモンバランスを乱す原因となるため、妊活中は納豆はダメと言われています。
エストロゲンは、主に卵巣から分泌されるホルモンです。主に下記のような作用があります。
- 女性の生殖機能の維持
- 子宮内膜を厚くする
- 生理周期を調整する
- 骨の健康や血管の健全性を保つ
- 女性らしい体形を形成する
このエストロゲンと大豆イソフラボンは分子構造が似ており、体内のエストロゲン受容体(ER)に結合して、エストロゲンと類似した効果を発揮します。
適量であれば、ホルモンバランスを整える効果も期待できますが、過剰に摂取してしまうとホルモンバランスが乱れてしまうため、妊活中は控えたほうが良いとされています。
過剰摂取はホルモンバランスを乱す可能性がある
厚生労働省によると、大豆イソフラボンの1日の摂取上限は、70~75mgとされています。
摂取上限を超えた量を継続的に摂取すると、女性ホルモンのバランスが崩れ、不正出血や生理周期の乱れを引き起こす可能性があります。
特にサプリメントでイソフラボンを摂取している場合、納豆など食事からの摂取量と合わせると過剰摂取になりやすいため、注意が必要です。
なお、納豆は1パック当たり約36mgのイソフラボンが含まれており、2パックで上限値に近づいてしまうことから、1日1パック程度が安心な摂取量とされています。
納豆が妊活にあたえる3つの効果

納豆には妊活に役立つさまざまな栄養素が豊富に含まれており、適量摂取することで、むしろ多くのメリットが期待できます。
ここでは、主な3つの効果を紹介します。
- ホルモンバランスを整える
- 血流改善作用
- 腸内環境・免疫サポート
1.ホルモンバランスを整える
納豆に含まれる大豆イソフラボンは、女性ホルモンの「エストロゲン」と似た働きをすることが分かっています。
エストロゲンは適量であれば女性の生殖機能の維持や、生理周期を整える効果があるとされています。
そのため、大豆イソフラボンには、女性ホルモンのバランスを整える効果が期待できます。
体内のエストロゲンの分泌が不足している時は、イソフラボンが補完的に働き、反対にエストロゲンの分泌が過剰な時は、抑制的に作用するという調整機能があるのも嬉しいポイントです。
2.血流改善作用
納豆には「ナットウキナーゼ」という、納豆特有の酵素が含まれていることが大きな特徴です。
このナットウキナーゼは、血液中の血栓(血のかたまり)を分解する作用があることが研究で示されており、血流をサラサラに保つ効果が期待できます。
血液の流れが良くなることで、子宮や卵巣まで適切に酸素や栄養が運ばれるため、妊娠しやすい体づくりにも役立つでしょう。
3.腸内環境・免疫サポート
納豆は発酵食品として、腸内環境を整える効果があります。腸内環境の改善は免疫機能の向上につながり、妊娠しやすい体づくりに役立つでしょう。
また、納豆には鉄分(1パック約1.5mg)や、カルシウム(1パック約40mg)、マグネシウムなどのミネラルも豊富に含まれており、妊活中の栄養補給にも効果的です。
妊活中におすすめ!納豆の食べ方のポイント

妊活に納豆を効果的に取り入れるための、食べ方のポイントを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
- 適量を守る
- 加熱せずに食べる
- 栄養バランスを意識して「ちょい足し」する
適量を守る
妊活中の納豆の摂取量は、1日1パック(約40~45g)が理想的です。これにより、イソフラボンの摂取量が約36mgとなり、1日の推奨上限(70~75mg)の範囲内に収まります。
ほかの大豆製品(豆腐、豆乳、味噌など)を1日で複数摂取する場合は、全体のイソフラボン量を適宜調整してあげましょう。
例えば、豆乳1杯(200ml)には約41mgのイソフラボンが含まれているため、納豆と同時摂取する際は量を控える、ほかの大豆製品は摂取しないなどの注意が必要です。
加熱せずに食べる
納豆に含まれる「ナットウキナーゼ」は、血流を改善し血栓を分解する働きが期待できる酵素です。しかし、熱に弱く、加熱するとその作用が失われやすくなります。
納豆汁や納豆チャーハンなど、加熱して納豆を食べる場合、70度を超えるとナットウキナーゼは死活してしまうため注意が必要です。
なお、納豆菌自体は90度程度(納豆汁など)であれば、基本的には死滅しないため、問題ありません。
しかし、100度以上で調理(フライや炒め物など)をする場合には、ある程度死滅してしまうため注意しましょう。
ナットウキナーゼの血流改善効果を最大限活かすには、加熱せずにそのまま食べるのが最も効果的です。
栄養バランスを意識して「ちょい足し」する
納豆を食べる時は、ほかの食材を「ちょい足し」することで栄養バランスを向上させることができます。
例えば、「キムチ+納豆」なら、発酵食品同士の組み合わせで、腸内環境の改善効果がアップします。
また、「アボカド+納豆」なら、葉酸やビタミンCが豊富なアボカドを一緒に摂取することで、妊活中に必要な栄養素を効率よく摂取できるのでおすすめです。
ほかにも、青ネギや大葉などの薬味をプラスすることで、ビタミンCやβカロテンを補うことができるので、ぜひちょい足しにも注目してみてください。
妊活中に納豆を食べる時の注意点

納豆は妊活におすすめの食品ですが、食べる時にはいくつか注意点があります。
ここでは、主な注意点を3つ紹介します。
- アレルギーや消化不良
- 塩分・糖分の摂り過ぎ
- 栄養バランスの偏り
アレルギーや消化不良
妊活中や妊娠初期には、アレルギーが発症しやすくなる場合があります。
もし、納豆を食べて口の周りに発疹が出たり、呼吸が苦しくなったりするといったアレルギー症状が出た場合には、納豆の摂取を止め、医療機関を受診しましょう。
また、納豆を食べたあと、お腹が張ったり下痢をしたりする場合は、消化不良を起こしている可能性があります。その場合は、摂取量を減らすか、摂取量を控えることを検討しましょう。
消化不良の症状がある場合は、納豆を細かく刻んだり、ほかの食材と一緒に摂取したりすることで改善される場合があります。
体調に合わせて無理をせず、必要に応じて医師や管理栄養士に相談することが大切です。
塩分・糖分の摂り過ぎ
納豆に付属しているタレには、塩分が多く含まれています。
妊活中~妊娠中は、高血圧や浮腫のリスクがあるため、タレの使用量を控えめにするか、薬味やほかの調味料で味付けを工夫しましょう。
また、甘いタレや砂糖を入れる場合も、糖分の摂り過ぎに注意が必要です。砂糖などに含まれる糖分には、身体を冷やしたり、胃腸を弱らせたりする可能性が指摘されています。
また、糖分の過剰摂取による血糖値の急上昇が起こると、肝臓からインスリンが大量に分泌され、今度は血糖値が急降下します。
血糖値の急上昇・急降下を繰り返すと、インスリン抵抗性という状態になってしまい、排卵障害を引き起こす可能性が高まるため注意が必要です。
塩分や糖分の摂取量に気をつけるためにも、自然な旨味を生かしたシンプルな味付けで楽しむようにしましょう。
栄養バランスの偏り
「納豆が体に良いから」と、納豆だけに偏った食生活は避けましょう。妊活中は、多様な食品からバランスよく栄養を摂取することが重要です。
タンパク質が豊富な食品ではありますが、肉や魚、卵なども取り入れるようにしましょう。
また、納豆にはビタミンCや一部のミネラルが不足しているため、野菜や果物、そのほかの食品と組み合わせて、総合的な栄養バランスを心がけるのがおすすめです。
妊活中で納豆以外にもダメな食品はある?注意が必要な飲食物6選

納豆よりも、むしろ妊活中に注意してほしい食品がいくつかあります。
ここでは、妊活中に注意が必要な飲食物を6つ紹介します。
- 生もの・加熱していない食品
- トランス脂肪酸・加工食品
- アルコール・カフェイン
- ビタミンAが多く含まれる食品
- 大型魚・海藻類
- 塩分・糖分・脂肪分の多い食品
1.生もの・加熱していない食品
生肉や生魚、生卵は、食中毒を引き起こす細菌が付着している可能性がある食品です。
食中毒に感染すると、発熱やリンパ節の腫れなどの症状が表れますが、この炎症が卵巣機能に影響することで、不妊のリスクを高めると言われています。
生ものを食べること自体は不妊のリスクにはなりませんが、リスクを避けるためにも、妊活中は生ものを控えたほうが安心です。
食中毒の原因となる細菌は加熱することで死滅するため、妊活中から加熱調理を心がけていきましょう。目安として、中心部温度75度で1分間の加熱がおすすめです。
また、生ハムやスモークサーモン、加熱されていないナチュラルチーズも同様の理由から摂取を控えるよう指導されることがあります。
2.トランス脂肪酸・加工食品
マーガリンやショートニングを使用した菓子パン、揚げ物、ファストフードにはトランス脂肪酸が多く含まれています。
トランス脂肪酸は排卵障害やホルモンバランスの悪化を引き起こすという研究結果があり、妊娠率に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。
また、インスタント食品やレトルト食品も添加物や塩分が多いため、注意が必要です。成分表記などを参考に、なるべく添加物や塩分が少ない商品を選ぶように心がけましょう。
3.アルコール・カフェイン
アルコールは妊活中から控えることが強く推奨されています。アルコール摂取は不妊リスクが高まるとされています。
妊娠が成立した場合にも流産や死産、先天異常が生じるなど、胎児への影響があるため特に注意が必要です。
また、カフェインも過剰摂取(1日300mg以上)は避けるべきです。一般的に、カフェインを摂取する量が多いほど、妊娠率が低下すると言われています。
体外受精では、カフェインの摂取量による妊娠率や出産率にそれほど差はなかったとされるデータもありますが、できればノンカフェインに置き換えたり、1日1〜2杯程度に抑えたりといった工夫をするのがおすすめです。
カフェインは、コーヒーや紅茶、エナジードリンクなどに多く含まれているため、1日の摂取量に注意していきましょう。
4.ビタミンAが多く含まれる食品
動物性ビタミンA(レチノール)の過剰摂取は、胎児の奇形リスクを高める可能性があるため、控えるようにしましょう。
例えば、レバーやうなぎ、あん肝などビタミンAを多く含む食品は、妊活中からの摂取量に注意が必要です。
ただし、植物性のβカロテンは、体内で必要量のみビタミンAに変換されるため、緑黄色野菜からの摂取は安全とされています。
5.大型魚・海藻類
マグロやカジキ、サメなどの大型魚には水銀が含まれていることがあるとされており、胎児の神経発達に影響を与える可能性があります。
キンメダイやメカジキ、クロマグロは週1回(約80g)まで、キダイやマカジキなどは週2回までが目安です。
また、昆布やひじきなどの海藻類はヨウ素を多く含むため、甲状腺機能への影響を考慮し、過剰摂取は避けるようにしましょう。
6.塩分・糖分・脂肪分の多い食品
漬物やスナック菓子、ケーキ、加工肉などは塩分や糖分、脂肪分が多く、肥満や高血圧の原因になります。
これらは妊娠しにくい体質を作る原因となることもあるため、適量を守った食生活を心がけましょう。バランスのとれた食生活を維持することが重要です。
妊活中積極的に摂り入れたい栄養素

妊活中におすすめの栄養素を5つ紹介します。
これらの栄養素を意識的に摂取することで、妊娠しやすい体づくりをサポートしていきましょう。
- 葉酸
- 鉄分
- カルシウム
- ビタミンD
- タンパク質
葉酸
葉酸は、胎児の神経管閉鎖障害のリスクを軽減する重要な栄養素です。厚生労働省によると、妊活中から妊娠初期にかけて1日400μg(サプリメント由来)の摂取を推奨しています。
食品では、納豆のほかにほうれん草やブロッコリー、豆類に多く含まれていますが、食品中の葉酸は吸収率が低いため、サプリメントでの補給も検討しましょう。
妊活中におすすめの葉酸サプリについては、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
 葉酸サプリおすすめ10選!選び方や基礎知識、飲むべき理由など徹底解説!
葉酸サプリおすすめ10選!選び方や基礎知識、飲むべき理由など徹底解説!
鉄分
鉄分は赤血球の生成に必要な栄養素で、子宮や卵巣への酸素供給に重要な役割を果たしています。
妊活中から十分な鉄分摂取を心がけることで、妊娠中の貧血予防にもつながるためおすすめです。
特に、動物性の鉄分(ヘム鉄)は吸収率が高いとされています。
レバーや赤身肉などに豊富に含まれていますが、胎児の奇形リスクを高める可能性があるビタミンAの過剰摂取につながりやすい食品となっているので、1日当たりの摂取量を越えないよう注意しましょう。
植物性の鉄分(非ヘム鉄)は、ビタミンCと一緒に摂取することで吸収が促進されるので、デザートにイチゴやキウイ、グレープフルーツなどビタミンCが豊富な果物を添えるのが効果的です。
普段の食事から食べ合わせを工夫すると良いでしょう。
カルシウム
カルシウムは、骨や歯の形成だけでなく、筋肉の成長や神経伝達にも重要な役割を果たす栄養素です。妊娠中はより多くのカルシウムが必要となるため、妊活中から意識的に摂取しましょう。
カルシウムは、乳製品や小魚、緑黄色野菜、豆腐などに豊富に含まれています。
ビタミンD
ビタミンDはカルシウムの吸収を促進し、免疫機能の調節にも効果を発揮する栄養素です。最近の研究では、妊娠率の向上にも関連があることが示されているため、積極的に摂取しましょう。
ビタミンDは、魚類(サケ、サバ、イワシ)やきのこ類に多く含まれており、また日光浴によっても体内で合成されます。
ただし、食品や体内での合成だけでは不足しがちな栄養素のため、サプリメントでの補給も検討してみましょう。
タンパク質
タンパク質は、筋肉や臓器、肌や髪の主成分であるだけでなく、ホルモンや酵素、免疫細胞の材料にもなる栄養素です。
タンパク質には「アミノ酸スコア」というものがあり、体内で合成できない「必須アミノ酸」をバランスよく含む「質の高いタンパク質」を積極的に摂取していきましょう。
肉類や魚類、卵、大豆製品などを組み合わせて摂取することで、動物性・植物性の両方のタンパク質を取り入れられるのでおすすめです。
タンパク質は一度に大量摂取しても効率的に利用されない栄養素のため、一食あたり20~30gずつ摂取することを目標にしましょう。
胃が弱いなどの理由で消化に不安がある場合は、脂肪分の少ない鶏ささみや白身魚、豆腐などを選ぶと良いでしょう。
妊活中の納豆摂取についてよくある質問

妊活中の納豆摂取についてよくある質問3つをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
- 納豆は毎日食べても大丈夫?
- 納豆を食べるのにおすすめの時間帯は?
- 妊活中は男性も納豆の食べ過ぎに注意したほうがいい?
1.納豆は毎日食べても大丈夫?
基本的に、納豆は毎日食べても問題ありません。
1日1パック(約40g)を目安に続けるのであれば、大豆イソフラボンの過剰摂取になる心配はほとんどないため、妊活中でも安心して取り入れられるでしょう。
2.納豆を食べるのにおすすめの時間帯は?
納豆はどの時間帯に食べても良いとされていますが、ナットウキナーゼの血流改善効果は、深夜から早朝にかけて働くため、妊活中は夜に食べることがおすすめです。
また、朝食に取り入れる場合も、代謝が上がるだけでなく、タンパク質や葉酸などの栄養素を効率よく補給できるためおすすめです。
さらに、納豆は発酵食品のため、腸の働きを助ける効果も期待できるでしょう。
3.妊活中は男性も納豆の食べ過ぎに注意したほうがいい?
男性の場合、女性ほどイソフラボンの過剰摂取への心配はありませんが、適量を守ってバランスの良い食生活を心がけるようにしましょう。
納豆に含まれる亜鉛やセレンなどの栄養素は、精子の質や量の向上に効果があるとされています。妊活中はパートナーと一緒に、無理なく取り入れると良いでしょう。
まとめ:妊活中の納豆は適量を守ればOK!食べ過ぎには注意しよう!

本記事では、妊活中の納豆の摂取について詳しく解説してきました。
納豆は妊活におすすめな食品で、大豆イソフラボンによるホルモンバランスの調整、ナットウキナーゼによる血流改善などの効果が期待できます。
また、豊富な葉酸や鉄分など、妊娠しやすい体づくりをサポートする栄養素が豊富に含まれているという特徴もあります。
ただし、大豆イソフラボンの過剰摂取を避けるためにも、1日1パック程度の適量を守ることが重要です。
過剰摂取はホルモンバランスを乱す可能性があるため、ほかの大豆製品やサプリメントとの併用時は特に注意が必要です。
また、加熱せずそのまま食べ、野菜やほかの食材と食べることで、より効果的に栄養を摂取できます。
妊活中は納豆を含めたバランスの良い食生活を心がけ、不安な点があれば医師や管理栄養士に相談するようにしましょう。
妊活を進める中で「産み分け」に関心を持つ方もいらっしゃいます。産み分けの方法としては、性交のタイミングで調整するなどがあります。
最近では、産み分けに関心のある方の間で潤滑ゼリー(一般的に「産み分けゼリー」と呼ばれることもある)が話題になっています。
産み分けに関する詳しい情報や、こうした潤滑ゼリーなどについて気になる方は、こちらの記事もご参考ください。
 産み分けゼリーおすすめ5選!それぞれの特徴や口コミを解説
産み分けゼリーおすすめ5選!それぞれの特徴や口コミを解説